開発者の人材不足
人手不足に加えてRPG/COBOL経験者は募集してもなかなか集まりません。
教育するにしても今まで学校で学習してきた開発言語とは
ちがうRPGやCOBOLではとまどいモチベーションも上がりません。
このままIBMを使っていてもいいのだろうかという不安が出てくるのも当然です。

人手不足に加えてRPG/COBOL経験者は募集してもなかなか集まりません。
教育するにしても今まで学校で学習してきた開発言語とは
ちがうRPGやCOBOLではとまどいモチベーションも上がりません。
このままIBMを使っていてもいいのだろうかという不安が出てくるのも当然です。

定年退職などに伴う後継者育成問題は事業継続性にとって深刻な課題になっています。
このままで事業継続の問題に直面してからでは遅いのです。
ERPでは莫大な初期投資と高額な維持経費が必要だけでなく
社内ニーズへの臨機応変な対応が遅れてしまいます。

そこで今、注目されているのがオープン化です。開発者人口の多いオープン系への移行が検討されています。
しかしオープン系の他のプラットフォームへの置換えではSQLやメモリのヒープ・サイズの制限の制約などにより企業情報管理に特化していたIBMに比べてパフォーマンスやハードウェア、OSの脆弱性により多くの企業がオープン系への移行に失敗しています。
日本は米国のようなトップダウン式の経営ではなく社員の声を反映したボトムアップの経営であり社内システムも多くの社員の声が反映されており容易に他の言語に置き換えられるものではありません。

今や開発者市場で最も多いのはJavaを抜いてPythonです。
学校で最初に教える言語もJavaではなくPythonです。
2023年の統計によればJavaよりPythonの開発者が
№1となっています。
学校で最初に教える言語もJavaではなくPythonです。
これからの社内開発をPythonで開発できるようにしておけば
開発者も人材豊富なPythonプログラマーの中から選ぶことができます。
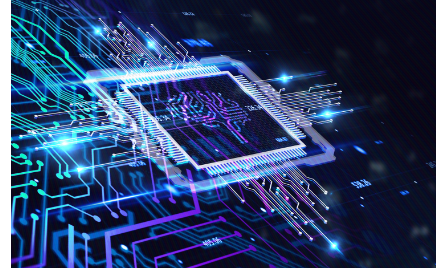
ハードウェアをUNIXやWindowsサーバーに替えることがオープン化ではありません。
開発言語をオープン系に進化させることがオープン化です。
これまで蓄積してきた膨大な社内ソフトウェア資産は
貴重であり莫大なコストがかかっています。
この貴重な社内資産を生かしつつオープン系の開発言語に
少しずつ段階的に移行していくことが成功する真のオープン化の道です。

Pythonは今やあらゆるプラットフォームで使われています。
 コンパイル不要のインタプリタ言語
コンパイル不要のインタプリタ言語 オブジェクト指向でRPG/COBOLとの共存、連携が可能。
オブジェクト指向でRPG/COBOLとの共存、連携が可能。 誰でも見やすくわかりやすいソースになります。
誰でも見やすくわかりやすいソースになります。 文法がシンプルで習得がカンタン。
文法がシンプルで習得がカンタン。 Pythonプログラマーを集めやすい。
Pythonプログラマーを集めやすい。
Pythonはいくつかの文法を覚えるだけですぐにでも書けてしまうほど簡単な言語です。
ある RPG III だけの経験の初老のプログラマーが会社の命令でわずか半年足らずで一人で
社内用のWebシステムを開発したという実例があります。
これに加えてPython.400を利用すればRPGの数分の一のソース・コードで開発ができてしまいます。
Python.400は長年の開発経験が蓄積されたフレームワークです。
またPython.400はRPG/COBOLプログラマーよりむしろPythonプログラマーにとってわかりやすいようにオブジェクト指向のプログラミングに指向されています。
富士通がメインフレームから撤退するのをご存じでしょうか?
2029年までに富士通はすべてのメインフレーム業務から撤退すると発表しました。
かつてはIBMと競っていたNECも今はIBMの販売代理店です。
企業向けサーバーは今後ますますIBM中心に集約化されていく方向になるでしょう。
脱IBMどころか今後は企業サーバーはますますIBMに集約されていくことでしょう