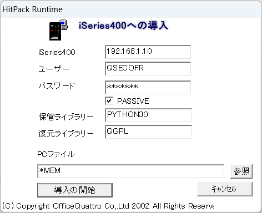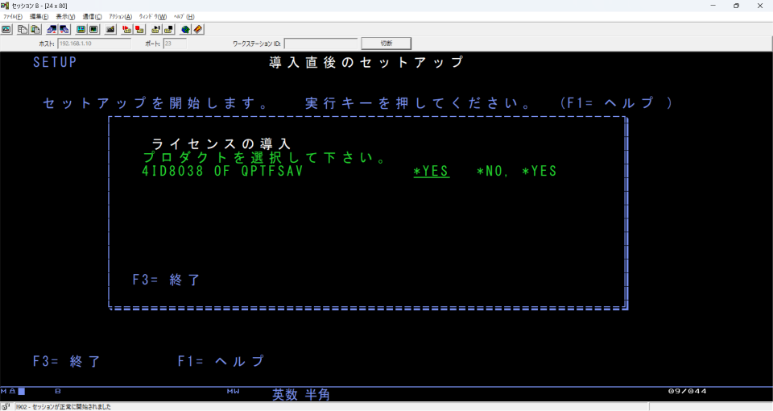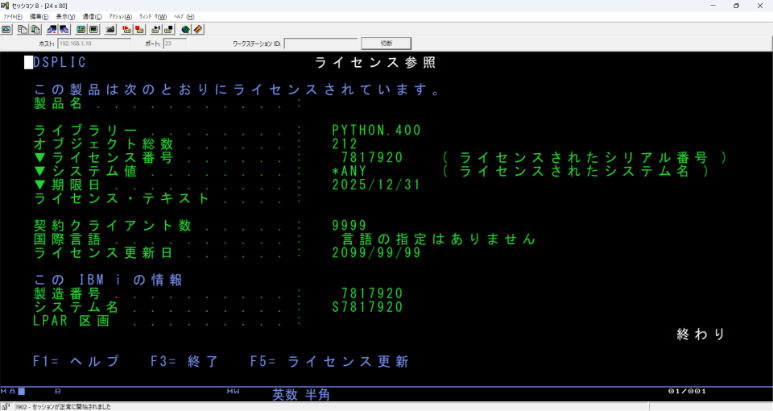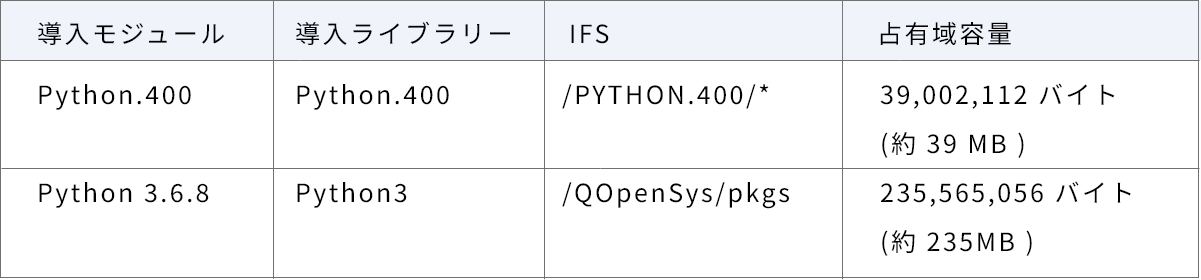IBM OS に対する Pythonの導入状況
IBMのオープン・ソース・プロジェクトの一環として各OSバージョンで
Pythonがプレ・インストールされている場合があります。
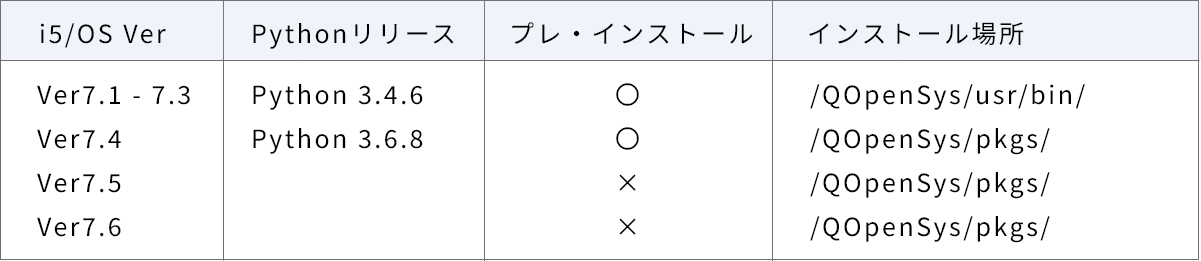 ※ Ver7.4 では /QOpenSys/pkgs/が一般のユーザー・パスとして登録されていませんのでPythonが導入されていたとしても一般ユーザーからはアクセスすることができません。
※ Ver7.4 では /QOpenSys/pkgs/が一般のユーザー・パスとして登録されていませんのでPythonが導入されていたとしても一般ユーザーからはアクセスすることができません。
このためPythonのインストーラはVer7.4ユーザーにはすべてのユーザーに共通なPROFILEを導入時に追加します。